再び台湾から飛騨にもどり、10月17、18日に岐阜の飛騨古川で行われたヒダクマ祭り。その2日目の様子を記録しておきます。もう1ヶ月以上も経ってしまい遅くなってしまいました。理由が2日目がとても面白く書くことが多かったのです。が、どこまで突っ込んで書いて良いのか分からず、消してしまいました。。。
気になる方はちょっと覗いてみてください!
目次
早起きしての散歩
昨日は東京から車で向かうため4時起きした結果、早めに就寝。そして、今日も早起きしました。前日の様子はこちら
6時に宿を出て、朝食までの時間を散歩することにしました。宿泊先で散歩が1番面白いと思っているので、歳を取っても楽しめそうです。なお、私の趣味は散歩です。
午前中は飛騨の匠を訪ねるツアーに参加
当日の申し込みで参加が可能だったため、少し早めの9:30にfabcafeHIDAに集合し、「飛騨の匠を訪ねる」ツアーへ参加してきました。
今回これに参加し、色々な体験や会話ができたことが1番面白かったです。
参加した内容は下記のものです。
飛騨の木を知るオプショナルツアー2日目 飛騨の匠を訪ねる
日時:10月18日(日)9:30-12:00
講師:金子公彦(金子工務店/大工棟梁)/堅田恒季(calm’s/木工職人)
料金:前売り 1,500円 (当日 2,000円)
定員:10名(定員に達し次第締め切らせていただきます)
ツアーの内容:
飛騨の匠の技術と心意味を受け継ぐ大工棟梁・金子公彦さんからの飛騨の自宅兼工務店にお邪魔し、大工の技と暮らしを学びます。
飛騨高山の大手家具メーカーを独立し、木工房とカフェを営む木工職人、堅田恒季さんに木工職人の仕事についてうかがいます。
金子工務店を訪問
まず金子工務店へ訪問し、金子さんから大工のお仕事を教えていただきました。
まず組み木のご説明から。
「おい、そこの兄ちゃん、この組み木を外してみろ!」
(ああ、これ今朝の散歩で見たやつだ!)
と、いった流れがから始まった金子さんの説明。組み木を外した状態が上の写真です。工具も使わず手で外すことができる組み木ですが、見事に私が呼ばれて組み木を分解したのですが、入り組んでいて外すのが難しかったです。
今朝の散歩で、ほとんどの家にこの白く塗られた雲のような模様が、この地方特有の文化なのか、意味があるものだったのか、知りたくくて気になっていた部分。
金子さんから「雲のような絵は大工さんのサインのようなもの」とのこと。こちらにも説明があります。また面として白く塗らているのは、割れ防止のために。今朝、気になったことを教えてもらえて嬉しかったです。
作業場の様子
捨てているわけでなく、寝かして乾燥させている木々たち
外に積み上げられた木は、要らない木なんだろうと思っていましたが、これらは自然乾燥を経て、辺材を腐らせつつ、心材を利用していくとのことです。
不要な木ですか?と聞いてしまって、すいませんでした。
男は家で遊ぶべし!?
一通り外の作業を見せていただいた後に、金子さんの「家の中も見て下さい、沢山遊んでいますよ。」といった案内。
お言葉に甘えてお邪魔してきましたが、一般の家庭ではない、大工さんのお家ならではの楽しい場がありました。(但し、どこまで掲載して良いのか分からないため、少しだけ写真を乗せておきます。)
玄関
写真がちょっとわかりにくいのですが、金子さんが手を添えている大きな柱。芯持ち材の木を使っている場合、背割りといってあらかじめ木に割目を入れておきます。参考はこちら
ただ、この柱はその背割りがはいっていません。
金子さんのお話では「木が育った場所と同じような太陽の向きに使ってあげれば、背割りはいらない。」とおっしゃってました。これも木を知っている職人しか分からないお話で興味深かったです。
仏間
さてさて、お家の中におじゃまさせてもらい、まずは仏間を案内していただきました。
その仏間に輝く1枚板のテーブル。これが本当に黄金色に輝いていて、綺麗でした。
玉杢と雲杢の模様が陰影をつけていて、この位置から見上げると、富士山とそれにかかる雲のように見えるとのこと。確かに!
元々は表面の仕上げはウレタン系にしていたところ、漆塗り職人の方が「これは木に良くないから、漆で塗り直そう!」とのことで、塗ってくださったとのこと。これを聞いて、ギターのボディの「ポリッシュ仕上げ」と「極薄ラッカー仕上げ」の話に通じるなと思ってしまいました。
やっぱり木は切りだされた後も、空気と呼吸をして経年変化していくのですね。
この碁盤も木のいい匂いがしていたのですが、碁盤の足の形は下記の意味があると教えていただきました。知りませんでした。
碁盤の脚は、クチナシの実の形を模しており、「他人の対局に『口無し』ということ」を示唆している。
引用 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%81%E7%9B%A4
サウナ
なんと、家の中にサウナまで作ってしまったそうです。とてもニコニコと笑顔で話す金子さん。
(奥様はどう思っているのか、ちょっと心配になりました・・・。)
そして、カメラコレクション!?
これは内緒です・・・。覗いてみたい人は金子さんへ。
calm’sを訪問
つづいて、calm’sの堅田さんを訪問しました。
ここは工房とオシャレなカフェを併設させた素敵な空間なのです。
はじめに参加者の自己紹介をし、まずは工房の様子を見せていただきました。
工房

ノギスが懐かしかった
旋盤や圧着用のプレス機など大きな重機が沢山ならんでいたのが大学時代を思い出し、ちょっと懐かしかったです。
並べられた機械のほとんどは、中古機械とのこと。こういったサイトでも中古機械が並んでいますね。もちろん家庭用電源ではなく、200Vの電源でうごく機械達。切りくずを集める粉塵機も大きいのがありました。
カフェ
一通りご説明いただいたあと、併設されたカフェに集まりおいしいコーヒーをいただきました。
工房からカフェに戻った時に、コーヒーのいい匂いを感じ、参加者が「いいにおい~!」といって和んだのが面白かったですね。匂いが空間をガラッと変えた瞬間でした。
カフェには工房で加工された商品達が気軽に手にとってさわれる場になっています。木を触って、温もりを感じたり、木を加工している人と話せる場が併設されているのは、都会にはあまりない形態ですね。
その他、こんなものもあったり・・・。
このバレン、毎年12名で版画で刷ったカレンダーを作っているそうです。1人1月を担当するそうです。人によってバラバラにもなりそうですが、昭和っぽい広告のような絵を入れたりと、作っている人達が楽しんでいる様子が伝わってきました。
印象的だったこと
家具で使われる木のほとんどは外国産
堅田さんとお話したときに、家具として作られる木材のほとんどは、山から木を切り倒してもってきた木ではなく、海外から仕入れた木を使用しているとおっしゃってました。
理由は広葉樹が少ないこともあるのかと思います。針葉樹や広葉樹の違いをまったく把握してなかったため、こういった事実を全く知りませんでした。
参考:日本の家具業界が衰退した愚か過ぎる理由【花粉症・土砂崩れという負債】
また私が大好きなアッシュやメイプル、マホガニー、ローズウッドは全て海外の広葉樹でもありました。
領域を横断した情報交換
今回のツアーで、偶然にも大工職人と家具職人と参加者の林業組合の方のお話を聞く機会にめぐまれました。
そもそも、木に関わる行程があまりにも違いすぎることもありますが、お互いの領域に関する情報の交換があまり無いのではと感じてしまいました。
でも、逆にこの分断されている領域が交わると、また新たな可能性もみえるのではと思いました。
これらを横断する役割の人達が地域に根づきながら物事や生活を考えていくことが、日本の色々なところで求められてくるのかなと感じ、私も協力できることを探していこうと感じました。
前日の様子
参考リンク
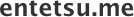



















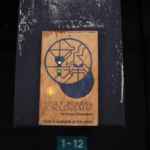










































No Comments